あかりをつけましょ、ぼんぼりに~♪
ひな祭りの代表的な歌の歌詞ですが、何気なく歌っているぼんぼりとは何でしょうか。
ひな壇の両脇にある、提灯(ちょうちん)みたいな丸いもの!
では、ぼんぼりと提灯の違いは?と聞かれると、うっっ・・と、言葉に詰まるかもしれません。
そこで今回は、ぼんぼりと提灯の違いをはじめ、昔の照明について調べてみました☆
ぼんぼりとは?

照明道具の一種で、行灯(あんどん)の仲間です。
そう聞くと、次は「行灯って何?」という疑問が湧きますね。
行灯とは?

照明道具の一種で、脚で照明部を支え、灯火を紙や布の火袋(ほぶくろ)でおおったものをいいます。
ぼんぼりは、この種類に属します。
提灯(ちょうちん)とは?

手で持って夜道を照らす、店先に吊るして周囲を明るく照らすなど、様々な使い方があります。
提灯の提は、手にさげて持つという意味です。
使わないときは、平たくたためるという作りも、物作りに長けた日本人ならではですね♪
ぼんぼりと提灯の違い

ぼんぼりには脚があり、床に置いて使うものに対し、提灯はぶら下げて使うものなんです。
ぼんぼりは現代でいう、スタンドライトやテーブルランプのようなもの。
提灯は、吊り下げ式の照明ですね☆
ぼんぼりの名前の由来

周囲を和紙で囲まれた炎は、たしかに「ほんのり」した、柔らかな灯りです。
これもぼんぼりの仲間!
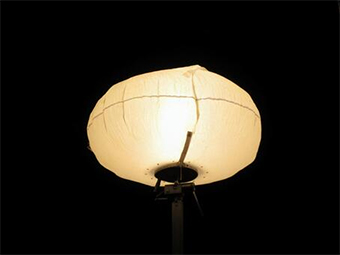


なぜ、ぼんぼりは雪洞と書くの?

・・・でしたら筆者と同じです(笑)
でも、間違いではありません♪
雪洞は「かまくら」または「せっとう」とも読みます。
雪洞と茶道の関係
雪洞と書いてぼんぼりと読む理由は、茶道に由来があります。
茶席でお客様がいないとき、湯釜を沸かす炉の炭を長時間保つために、炉に被せ物をします。
白い和紙をくり抜いて窓を作ったもので、これを「雪洞(せっとう)」といいます。
ぼんぼりは、この雪洞(せっとう)にヒントを得て作られた照明器具なんです。
江戸の灯り 大火と怪談
【大火】
電気が発明されるまで、人々の暮らしに火は欠かせないものでした。
喧嘩と火事は江戸の華、といわれるほど、江戸時代は火災が多かったのです。
和紙と木材で作られた照明器具の中に、油(なたねやイワシ油など)を入れて、火をつけます。
使う場所は、木造建築とイグサで作られた畳。
照明器具が倒れたら、火が燃え広がるのも早く、大火事になりやすかったのです。
【怪談】
ぼんぼり、提灯、行燈に江戸とくれば、怪談話を想像する方もいらっしゃるでしょう。
有名なところでは「四谷怪談」と「牡丹灯籠」がありますね。
四谷怪談は、大きな提灯に顔が描かれた絵画が有名で、インパクト大!
牡丹灯籠は、タイトルにも表紙絵にも灯籠があります。
この2作は「日本三大怪談」のうちの2つなので、興味がある方はぜひ読んでみてください♪
昔の灯り どんな種類がある?

簡単に一例をご紹介しますね。
・松明(たいまつ):松ヤニの多い所や竹、葦(アシ)などを束ね、火をつけて灯りをとる。
・篝火(かがりび):鉄の容器に松油で火を焚き、夜間の警護や、漁猟などに使う。
・蝋燭(ろうそく):綿糸やイグサを芯にして、蝋(ロウ)を溶かし固めたもの。
・行灯(あんどん):燭台に脚を付け、和紙などで火をおおったもの。床に置いて使う。
・提灯(ちょうちん):割竹を骨にし、周囲を和紙や絹を貼り付け、中にロウソクを置いて使う。
・ガス灯:ガスを燃料とした照明で、屋外で使うことが多い。
電気と電化製品が普及した現代でも、使われているものばかりです。
火鉢や囲炉裏との違い

同じ火を使う道具でも、照明道具、暖をとるもの、調理に使うものに分類できます。
現代のものに例えると・・・と考え、今人気のキャンプに例えてみました。
・焚き火・・・囲炉裏、カマド
・ウッドストーブ・・・火鉢
・ランタン、ヘッドライト・・・提灯
・キャンプ場の常夜灯・・・行燈(ぼんぼり)
といった具合でしょうか。
アウトドアで、焚き火を眺めてホッとするのは、DNAに刻まれた火への感謝と回顧の心かもしれません♪
昔の照明を身近に感じる方法

古典落語や、歌舞伎の舞台には、昔の照明であるぼんぼりや提灯、行燈などが登場します。
どんな風に使っていたのかも分かるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。
また、時代劇観賞や、江戸東京博物館もおすすめですよ♪
→ 江戸東京博物館


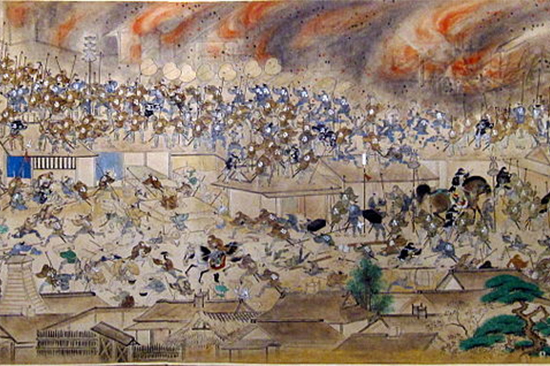























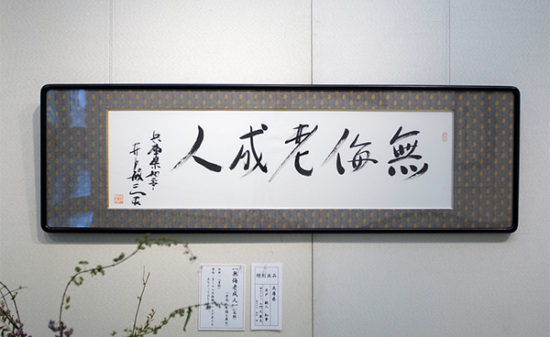
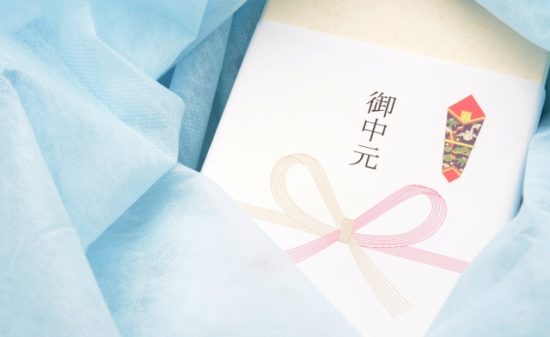














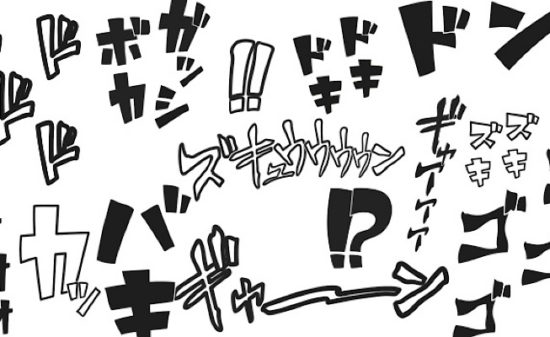

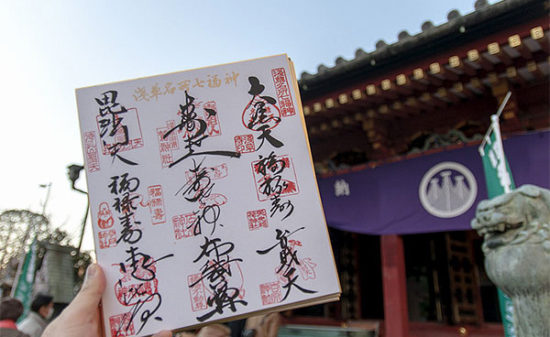

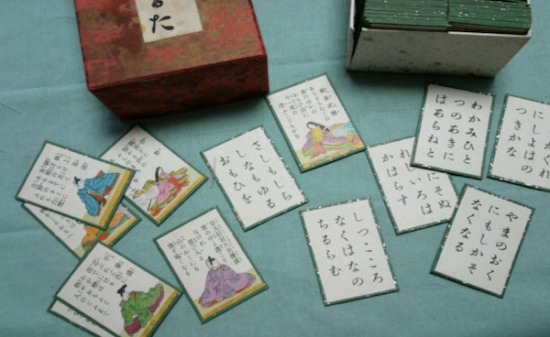














































































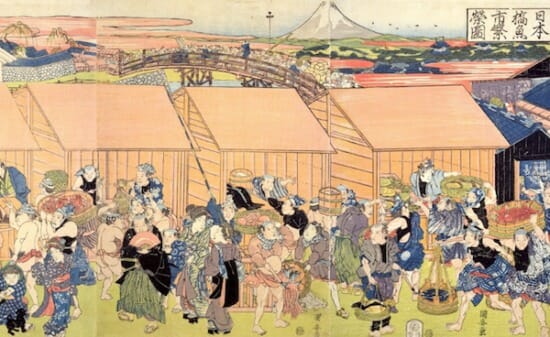











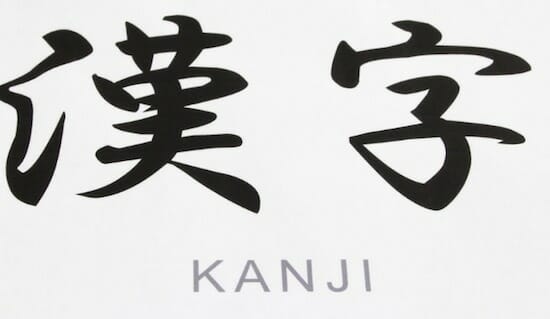


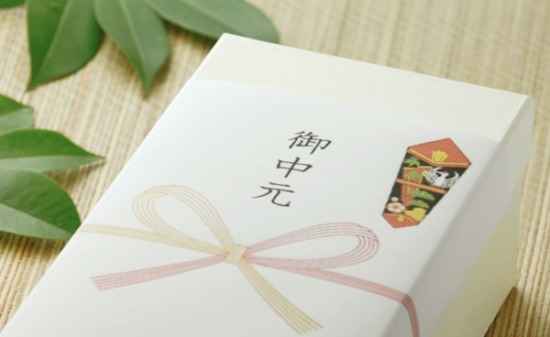













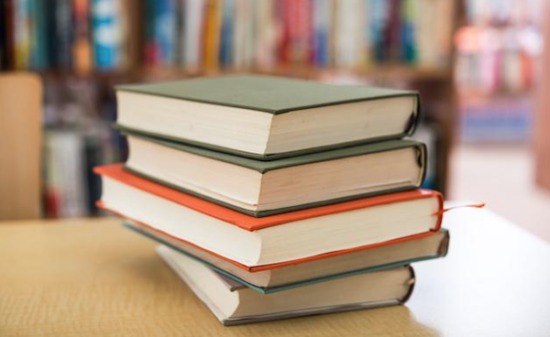





























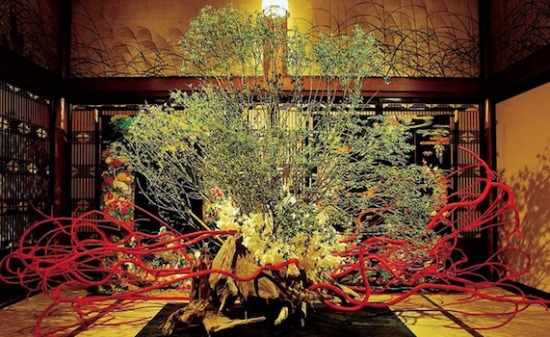



































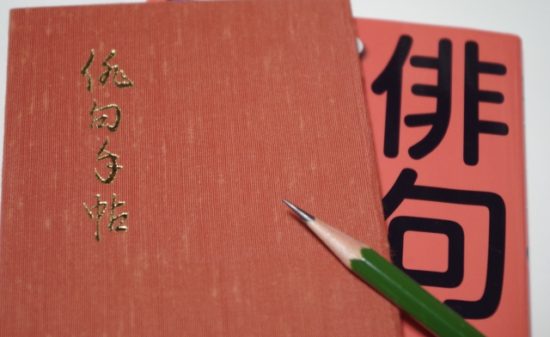


























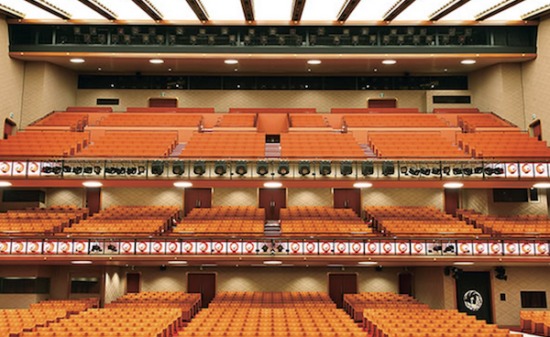





























































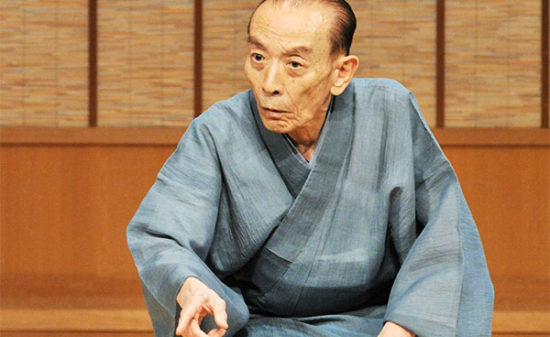






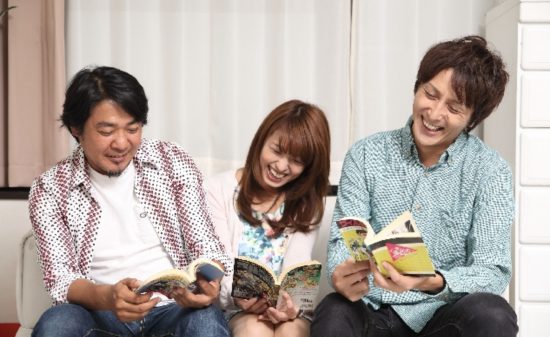


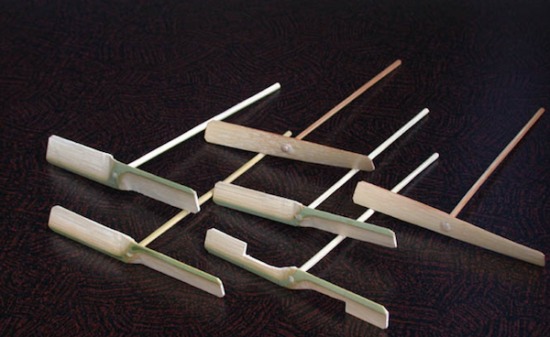




























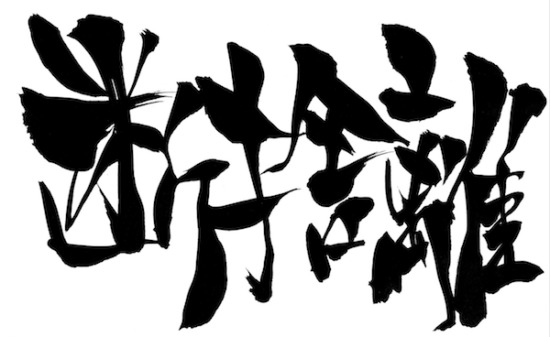







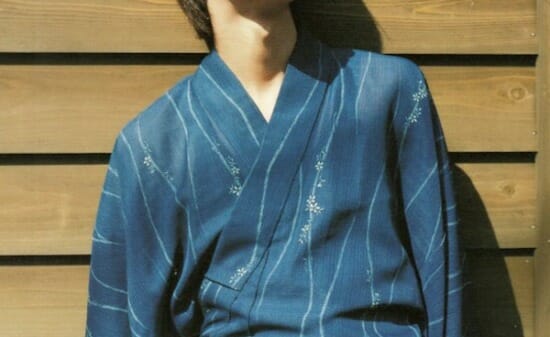







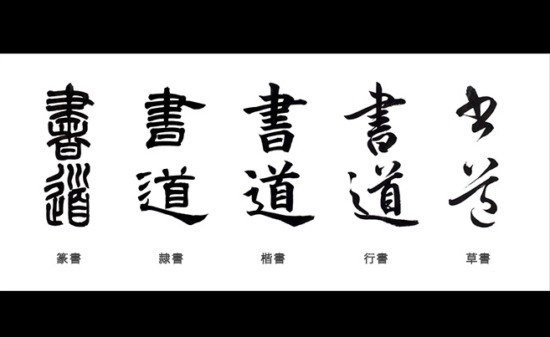


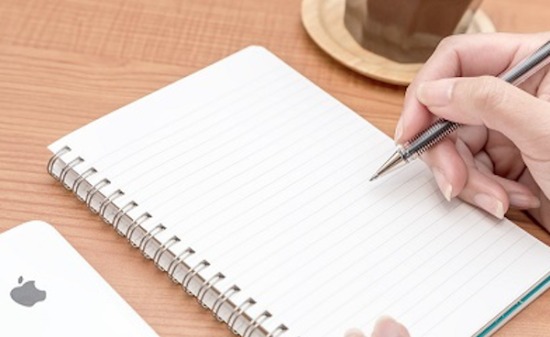


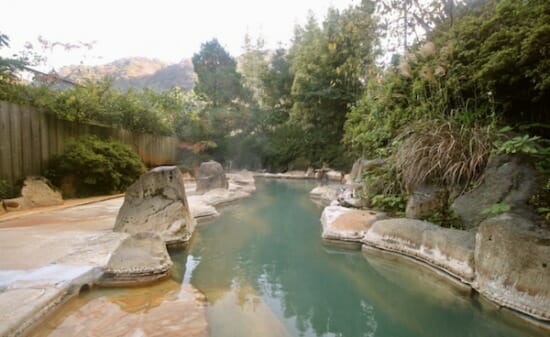

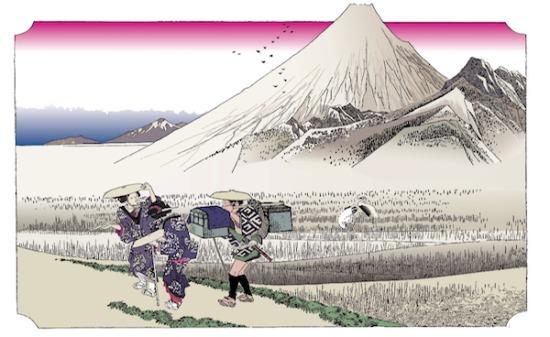

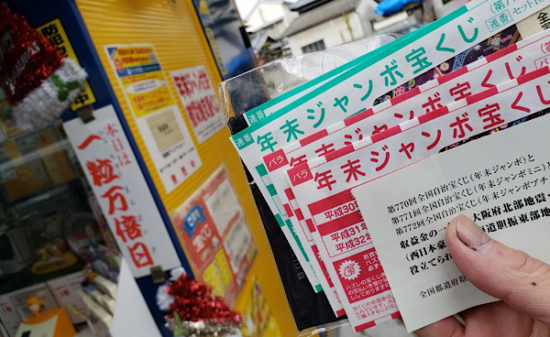






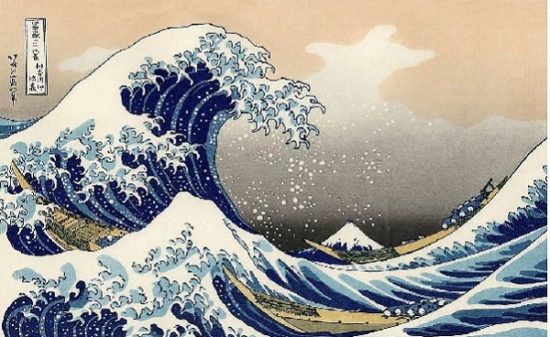
































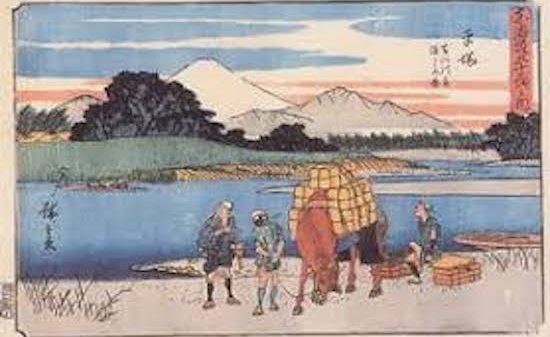


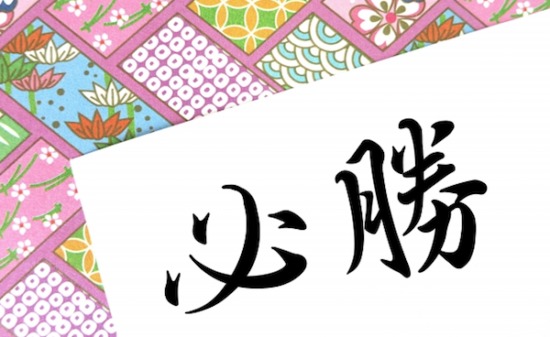


























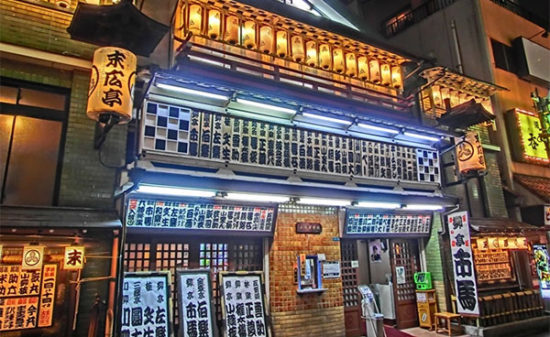

























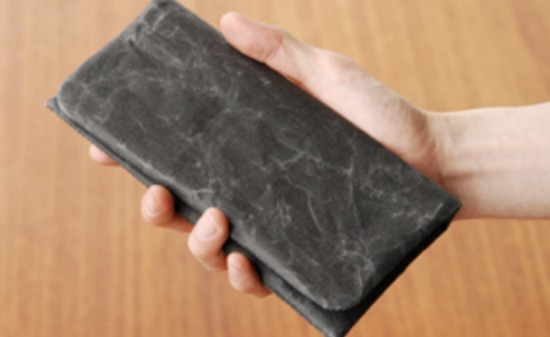

















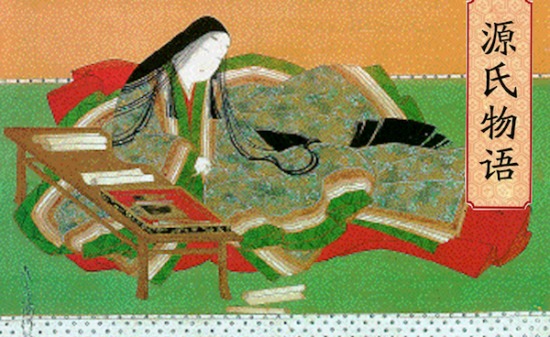





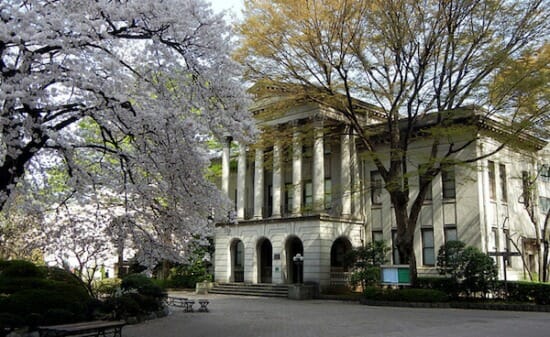


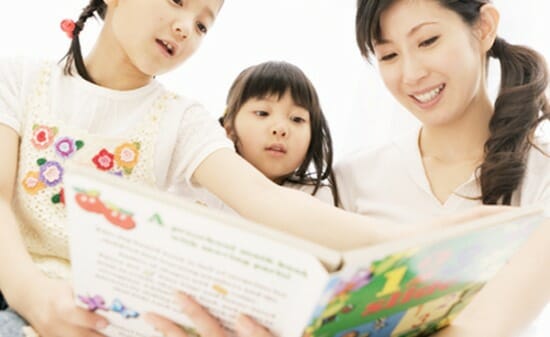














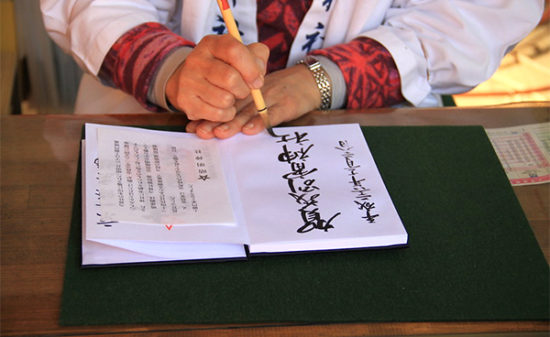







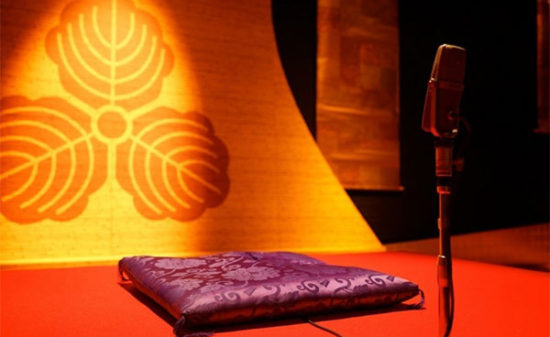




























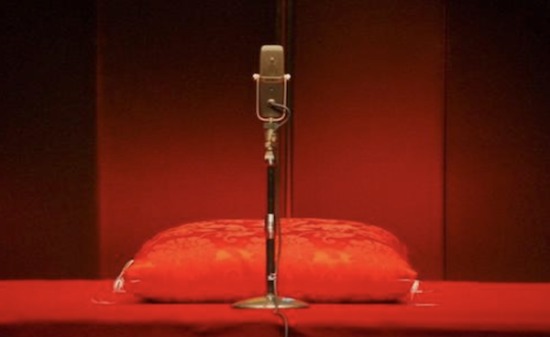





 PAGE TOP
PAGE TOP